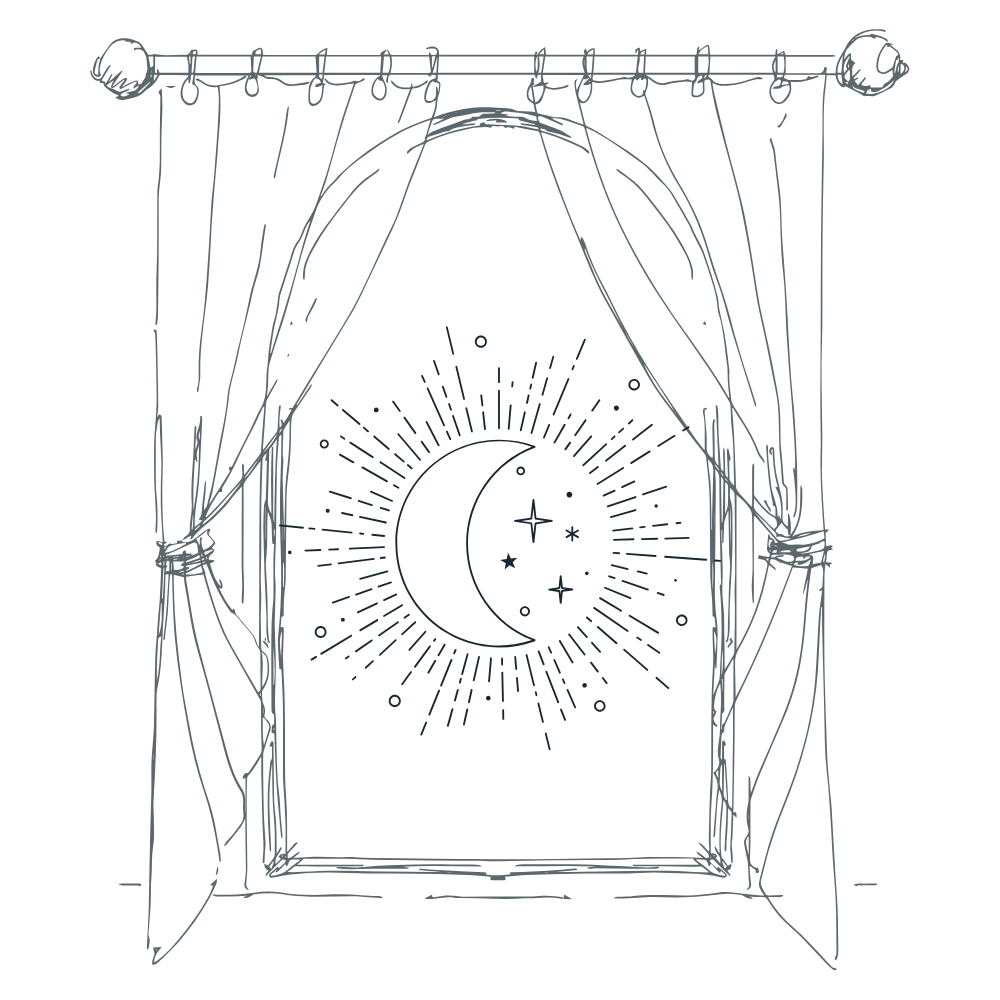ダメな自分を表明したいのは なぜか
褒められると否定したくなる気持ち
誰かに褒められると、途端にいたたまれない気持ちになって、否定したくなる。
自分はそんなにすごい人間じゃないんだと、周りの人たちを説得してまわりたくなる。
これは、自己評価が低いことに由来する衝動のような気もするけど、それだけではないような気もする。
そもそも自己評価とはなんだ。
自分で自分を評価すること。自分の中にはその価値基準があって、それに基づいて自分の価値を測っている。
自分で自分を、それなりに評価していたとしても、それはあくまでも自分の基準に基づく評価でしかなく、他人の基準によって評価されるものとは価値が変わる可能性がある。
自分の基準が高ければ、自己評価が低くなり、基準の低い他者から高い評価を得たりして、そのギャップに驚く。
この場合、自分はそんなに高い評価をつけられるような人間ではない、という自意識があるために、ダメな自分を表明したくなるのかもしれない。
周りからの評価と、自分の中の評価のギャップを埋めるために、周りからの評価を下げようとする。
そんなことをしていたら、いつまで経っても、自分に対する自分の評価は高くならない気がする。
であれば、自分の価値を認めたいのなら、他者評価と自己評価のギャップに直面したとき、修正すべきは自己評価のほうか?
これは果たして、怖いことなのだろうか。
それがなかなかできないのはなぜか。
自分に対する自分の評価基準を下げられないことが、自己肯定感にも影響するのか?
自己肯定感が低いということは、ある意味では、自分の評価基準のハードルが高いだけ、ということなのかもしれない。
それだけではない気もするけど。
これは単純に、自分が信じてきたもの、拠り所として人格を形成してきたかもしれないところのもの、自分に対する自分の評価基準が、揺るがされることによる不安、あるいは恐怖か?
それが、怠惰な自分を戒めるためのものであったならば、どうやら余計に怖いらしい。
であれば、怖がらずに、自己評価の基準を下げるために必要なことは何か。
基準を下げても大丈夫だと、大丈夫な自分だと、自分を説得することか?
あるいは、評価基準が高くなり過ぎた原因を解明し、そこにかかっているロックのようなものを外せば、基準を下げることができるのではないか。
自己肯定感が低い人、ダメな自分を表明したい人の中には、褒められても、そんなことは褒められるに値しない、自分にとってはできて然るべきことで、当たり前にこなすべきことだ、と感じる人が、一定数いるのだろう。
この、自分にできることはできて当然で褒められるほどのことではない、という感覚は、どこから、いつから生まれるのか。
単純に、理想と向上心が高いだけなのかもしれないし、幼少期から「それくらいはできて当然だ」と、何かを成しても褒められることもなく成長してきただけなのかもしれない。
これが、根源的に「褒められ慣れていない」ということなのかもしれない。
自分に対する評価基準が高いことは、そう悪いことでもないような気がする。
それで測ることができるのは、あくまでも、自分にとっての自分の価値だ。
そんなものは、自分の役にしか立たない。
そしてそれを自分の役に立てることで、成長が促されるのかもしれない。
そう悪くない。
社会生活を送る、という点で考えれば、自分で自分をどの程度評価しているか、ということには、あまり意味がないような気がする。
自分の価値を決めるのは、たいていの場合、他者で、他者はその人自身の価値基準に従って評価をつけてくるので、自己評価の基準など、考慮されない役立たずだ。
自分で自分を高めるために、自分で認められる自分であるために、高い基準に従って自分を成長させればいいのではないか?
結局は他者評価、なのかもしれないが、他者評価と自己評価のギャップに戸惑うかもしれないが、所詮他者からの評価など、自分の管轄外のものであって、自分の意志ではどうすることもできない。
多少、他者からの印象を良くすることはできるかもしれないが、他者の評価基準が他者自身の中にある、とても個人的なものなのだから、結局の所、自分の力だけではどうすることもできない部分があるし、そもそも他者の評価基準など理解することもできないかもしれない。
そんな、自分の力ではどうにもできないもの、自分の管轄外の何かに振り回されたり、影響を受けたり、自分の基準に合わせて他者の基準を修正させようと試みても、最終的には、どうにもできないような気がする。
であれば、他者に左右されない、自分に対する自分の判断基準に従って、自分を「自分で認めることができる自分」へと育てていった方が、最終的には頑丈な自己評価を得られるような気がする。
ところで、自己評価と他者評価の間のギャップに戸惑い、他者評価の基準が自分には理解し得ないものであると、他者から与えられるその評価に、どのような付加価値があるのか、ということに怯えているのかもしれないと思う。
例えば「すごい」と言われること、私にとっては「優しい」と言われること。
この「すごい」とか「優しい」という言葉が、他者にとってどのような意味を包含するものなのかがわからなくて、自分の価値基準に照らして、これまでに同じような言葉で評価されてきた人のことを想像して、怯えたりする。
「優しい」と評価される人は、どのような人間だと思われているのだろうか。
例えば、弱い者に手を差し伸べる人。多くの人が嫌がることも、積極的にこなす人。ダメな人間を受け入れる人。相手を思いやる人。多くの人に、愛情を注ぐ人。相手のために、行動できる人。
誰からも相手にされない自分にも、あたたかく接してくれる人。イヤなことをされても、笑って許してくれる人。
他者から「優しい」と評価されるとき、相手が何をもってその評価を下したのかがわからないとき、その評価が自分に対する自分の評価と一致しないとき、相手がその言葉に含めている意味を想像してみる。
相手にとっての「優しい」とは、何を意味しているのか。
「優しい」人間である私は、何を期待されているのか。
無闇な褒め言葉は、相手に期待を押し付けている側面があるのではないかと思う。あるいは、私自身が、勝手に何かを期待されているような気になっているのかもしれないけど。
私は、弱いからという理由で誰にでも手を差し伸べるなんてことはしないし、注げる愛情は限られているので、自分の好きな相手にしか注がない。
何が相手のためになるのか、なんて、突き詰めると私の想像でしかないと思ってしまうから、それだけを理由に行動したりはしない。自分のためになること、自分のやりたいこと、自分の役に立つこと、それが相手のためにもなりそうな場合、もしかしたら相手のために行動しているように思われることもあるのかもしれない、と思う。
誰からも相手にされてこなかった人間の、相手にされない理由が、その人の人間性にあるのだとしたら、私は多分、他の多くの人と同じように、そんな人間とは関わり合いになりたくない。
イヤなことをされたら怒るし、そんなことをする人は嫌いだ。ただ、私の中の「イヤだ」と思う基準は、私自身のものでしかないので、その基準が少しズレている相手にとっては、笑って許しているように見えるだけかもしれない。
それは、イヤなことを許しているのではなく、それについて「イヤだ」と思っていないだけだ。これは優しさか?
多くの人にとっての「イヤ」なこと、少なくとも、私を「優しい」と評するその人間にとっては「イヤ」なことを、私が「イヤ」だと思っていないのは、優しさか?
これは単純に、感覚の違いでしかないのではないか?
ただし、感覚が違うのだから、「優しい」という言葉に含ませる意味の幅に違いがあるのだから、相手のその基準に基づいて「優しい」と評価されるのであれば、受け入れるしかない。
私が受け入れ難いと感じてしまうのは、私には分かり得ない、相手の評価基準、「優しい」という言葉に付随して私に付与されているかもしれない「期待」のような何かだ。
だから、無闇に「優しい」と評価されるのが怖くて、面倒くさい。ただの「優しい」人間は、他人から面倒を押し付けられそうな気がする。遠慮の無い態度を向けられる気がする。それが、私が「優しい」という言葉に付与している価値で、「優しい」人間であることは、そのような面倒が降りかかってくるという事かもしれないと、私自身が勝手に想像している。
その点に基づいて、「私は優しくなんかない」と表明したくなるのかもしれない。少なくとも、それらのことを「面倒だ」と思ってしまう人間だ。
このように考えると、例えば、相手のことを自分も少し知っているような場合、あるいは、知っているような気がする場合、また、「優しい」と評される部分がより具体的で、具体的なその「優しさ」が、私の価値基準と一致しているように感じられる場合、相手からの評価を素直に受け入れることができるような気がする。
これは、「私のことをよく知りもしない人間が、軽々しく評価するな」という気持ちにもつながっているのかもしれない。
例えば、私の手に負えない問題を専門家に丸投げすること。これは、できないことをしようとしても時間の無駄だ、という私自身の観点から、丸投げすることが多いのだけど、それは結局、相手の時間を無駄にさせない、素人の的外れな考えに振り回されずに済む、という点で相手のためにもなる。
私の「面倒くさい」と、相手への「思いやり」に、たまたま重なる部分があって、お得なパターンだと思う。
だから、この行動を指して、これは「優しさ」だと言われることには、納得できる。私も優しい行動をすることができるんだなあと、少し嬉しい気持ちにもなる。
これには、幼少期から「優しくない」と評され続けていたことも影響している。なんだか複雑になってきた。
そして、この行動を指して「優しい」と評する誰か、この行動は「優しさ」だと言ってくれる誰か、その誰かにとっても、この行動は相手のためになると考えられるところのものなのだろうと思う。
つまり、私の感覚と、相手の感覚が、この点において重なっていると、私は感じたりする。
他者からかけられる期待について文句を言いながら、結局自分も誰かに期待しているのかと思うと嫌気がさすが、できるだけ余分な期待を含めずに、最小限にとどめようと理性を働かせながら、相手と自分の価値観には、少し似た部分があるのかもしれない、と思う。
そして、少し嬉しくなる。
これは、自分に「優しさ」があると評価されたことへの嬉しさでもあるが、自分の価値基準がほんの少し認められたような気がすることへの嬉しさでもあるのかもしれない。
また、自分のダメな部分、決して「優しい」とは言えない部分を、すでに知っている誰かから「優しい」と評価される場合。
ここには、「優しい」という言葉に、余計な期待が付与されてはいないかもしれない、という安心感がある気がする。
ダメな部分があっても、優しくない部分があっても、その中においても「優しさ」がある、ということを認められているような、安心と嬉しさ。
無闇な期待をかけずに、私の中の「優しさ」を認めてもらえる安心感。
それは、私のことをよく知らずに(というよりこれは、私が相手のことをよく知らないからでもあるのかもしれないが)、「優しい」という言葉に自分がどのような意味と期待を付随させているか認識していないかもしれない誰かから向けられる「優しい」という評価とは、まったく別物のように感じられる。
結局、自分という人間を理解してほしいだけなのかもしれない。
ダメな自分を表明したくなるのは、私という人間のダメな部分も理解した上での評価、私にとってより価値を感じられる評価を求めているからかもしれない。
ちょっと贅沢かもしれない。